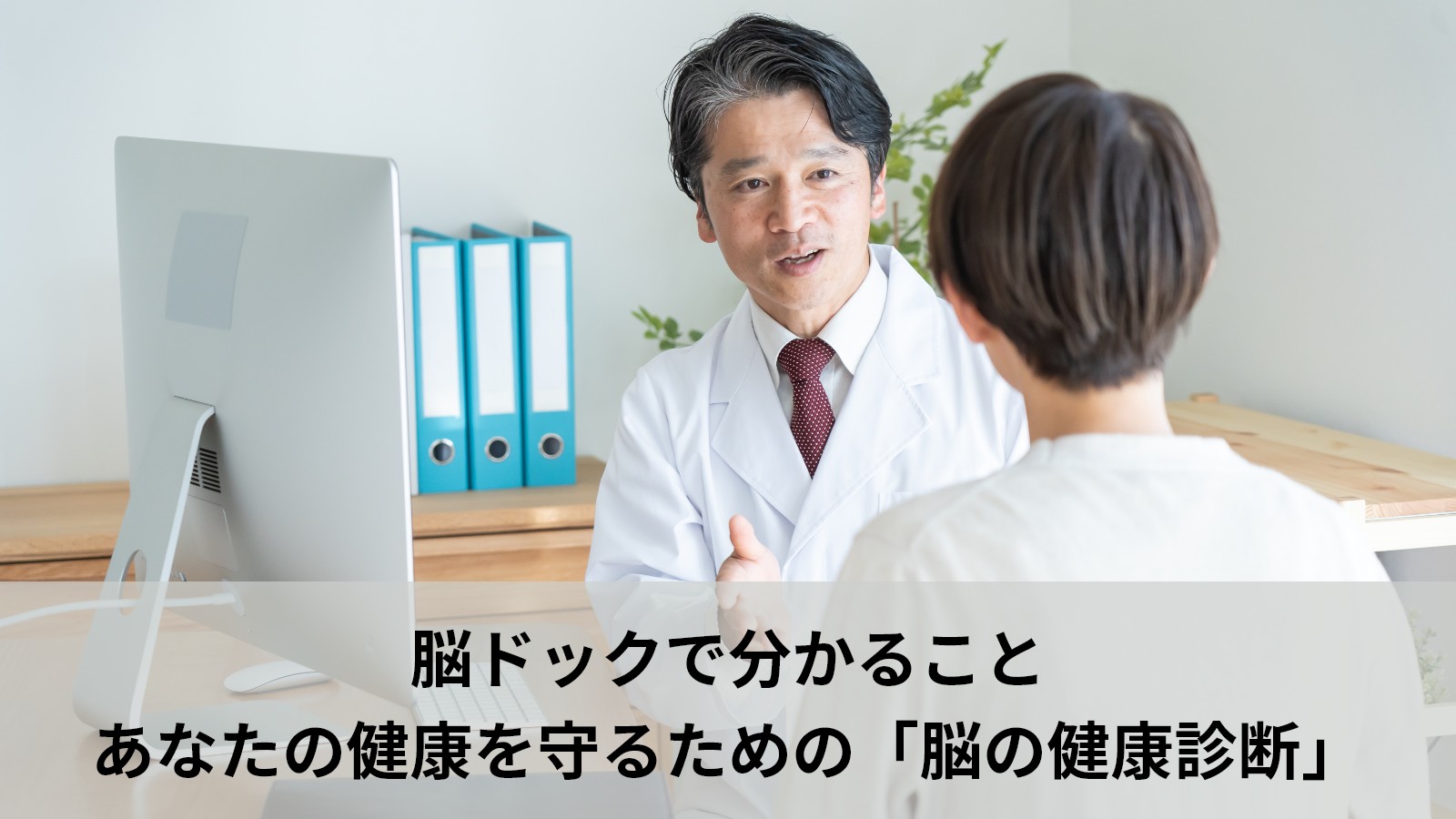脳ドックとは?
受けた方がいいケース、検査内容・医療施設と選び方を解説
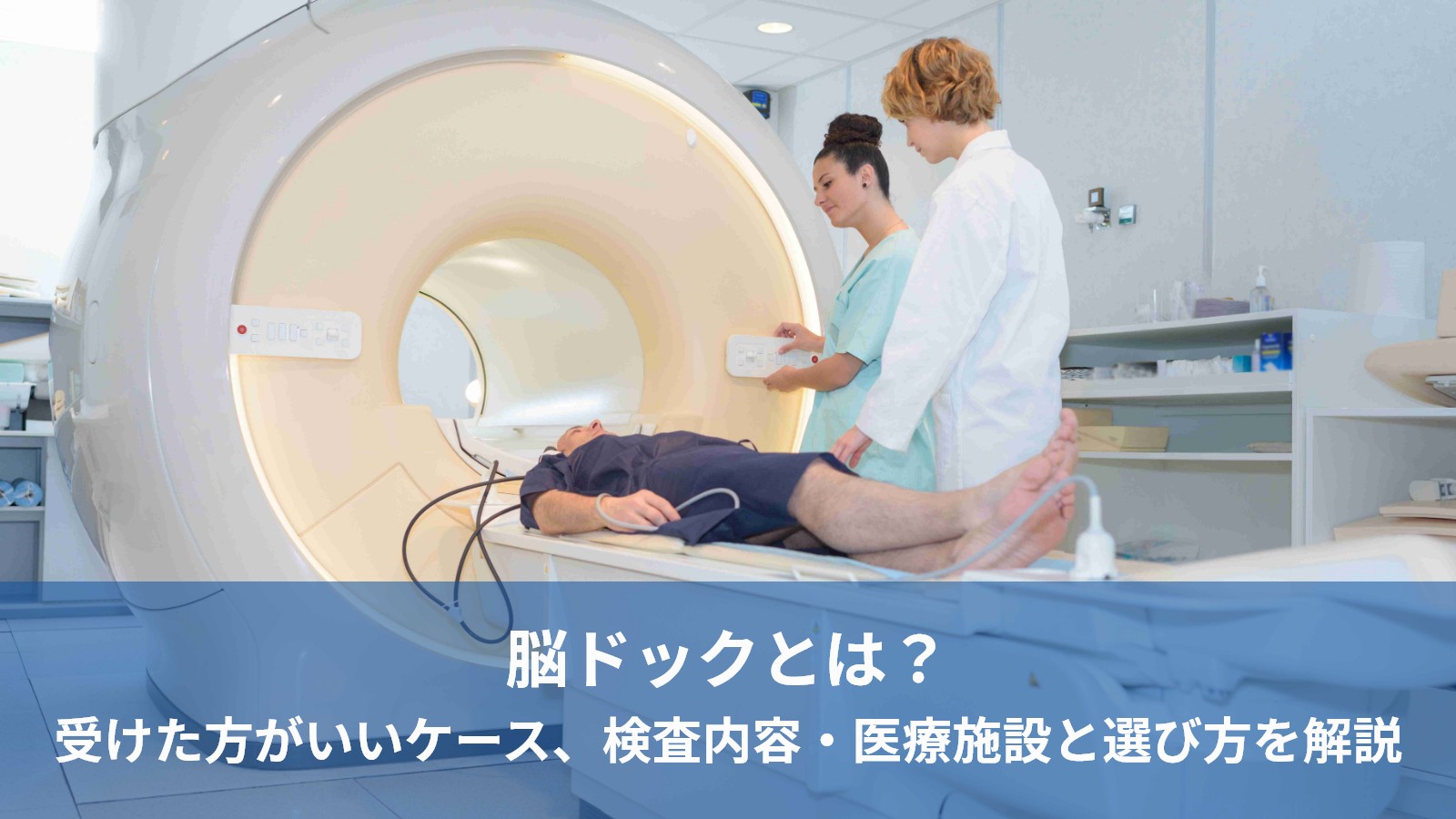
脳ドックは自分にとって必要?、検査項目にどんな内容があるの?、どのように病院・クリニックを選べばいいの?、といった脳ドックの「よくある質問」を徹底解説します。
Button脳ドックとは、脳ドック学会のウェブサイトによると「頭部MRI・MRA等を用いて脳に関係する疾患の診断や、疾患リスクの早期発見等を目的とする健康診断の一種」とされています。
通常、人間ドックでは脳の検査は網羅されておらず、脳の状態を詳しく調べるためには脳ドックが必要になります。
「脳血管疾患」は日本人の死因としては4番目の多さとなっており、2021年の脳血管疾患による死亡者数は10万4,595人にのぼります(2022年9月 厚生労働省「令和3年(2021)人口動態統計」)。脳血管疾患を発症する人は年間29万人以上と言われており、発症した人のうち、約3人に1人は亡くなっていると言える疾患です。
また、寝たきりになってしまう病気としては最多となっており、介護が必要になる病気としても2番目に多いと言われています。
脳ドックは自分にとって必要?、検査項目にどんな内容があるの?、どのように病院・クリニックを選べばいいの?、といった脳ドックの「よくある質問」を徹底解説します。
Button脳ドックで何が分かるのか、どのような病気や症状を発見できるのか、そしてコースやオプションの選び方について詳しく解説します。
脳ドックは一般的なコースで2~10万円程度(検査内容や病院・クリニックによって異なります)かかります。予防を目的としているため保険の適用外となり、全て自己負担となる「自由診療(※)」です。
このため「脳ドックを受けない方がいい、というのは本当?」「脳ドックのデメリットは何?」と思う方も多いのではないでしょうか。本記事では「脳ドックで後悔しないためのポイント」を解説します。
※症状がある場合など、医師が必要と判断した検査の場合、保険適用で脳ドック同様の検査を受けられる場合があります。
MRI検査は、正式には「磁気共鳴画像法検査」と言い、主に磁力を活用して撮影を行います。MRAとの違いや注意点、選び方などを詳しく解説します。